
TVドラマ「コンバット!」 エピソードガイド
グリーンアロー出版 (98.06.20) ¥2500
コンバットに関する本ではこれが最高のものであろう。
特に日本の書籍にはない、製作会社・スタッフについて
の詳細、撮影秘話、出演者の裏話などが豊富。
写真も多いのでファン必携の一冊。
関連書籍コレクション
 |
コンバット・クロニクル TVドラマ「コンバット!」 エピソードガイド グリーンアロー出版 (98.06.20) ¥2500 コンバットに関する本ではこれが最高のものであろう。 特に日本の書籍にはない、製作会社・スタッフについて の詳細、撮影秘話、出演者の裏話などが豊富。 写真も多いのでファン必携の一冊。 |
|
| (右)手に入りにくいみたいだなぁ… |
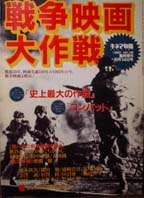 |
戦争映画大作戦 キネマ旬報1995年臨時増刊 キネマ旬報社1995.8.14 タイトルどおり戦争映画の特集だが、コンバットについて8ページ、他のTVドラマシリーズについて4ページ掲載。 コンバットの魅力を様々な視点から総括、2ページがデータページで、監督・出演者リストの他、 日本での放送順で152話放送日の一覧が貴重。 |
(右)その他 に「アメリカンTVドラマ50年」BSfan特別編集編、定価:2,000円 2003年3月 コンバットの記事が2ページにわたり載っている。 |
月刊・コンバットマガジン(株ワールドフォトプレス) 「コンバット!」が特集記事となっているもの。
| *あくまで私の調べた範囲です。 |
|
| 号数 | 特集記事 |
| 1980年8月創刊3号 | コンバットで使用された火器について |
| 1982年10月 | ヴィック・モロー死亡記事、1ページのみ |
| 1985年4月 | TVコンバットPART1 |
| 1986年2月 | TVコンバットPART2 “サンダース軍曹着せ替え大セット”← しょーもな!いらんかった! |
| 1987年4月 | ミリタリー入門、歩兵部隊の編成、ヘンリーとサンダースについて |
| 1992年10月 | コンバットの魅力。コンバットロジー・プロローグ |
| 12月 | コンバットロジー(第1回) サンダース軍曹 |
| 1993年2月 | コンバットロジー(第2回) ヘンリー少尉 |
| 4月 | コンバットロジー(第3回) カービー |
| 6月 | コンバットロジー(第4回) ノルマンディ上陸作戦における分隊の状況 |
| 7月 | コンバットロジー(番外編) |
| 8月 | コンバットロジー(第5回) ケーリー |
| 10月 | コンバットロジー(第6回) 特集・そこが知りたい 放送リスト |
| 12月 | コンバットロジー(第7回) ドイツ軍のユニフォーム 放送リスト |
| 1994年2月 | コンバットロジー(第8回) 使用火器 放送リスト |
| 4月 | コンバットロジー(第9回) ドイツ軍小火器 |
| 6月 | コンバットロジー(第10回) リトルジョン |
| 8月 | コンバットロジー(第11回) レジスタンス |
| 10月 | コンバットロジー(第12回) ヨーロッパ戦線の状況を検証 放送リスト |
| 12月 | コンバットロジー(第13回) 雑学百科1 放送リスト |
| 1995年2月 | コンバットロジー(最終回) 雑学百科2 放送リスト |
| 1997年1月 | 「コンポート‘96」レポート1 |
| 2月 | 「コンポート‘96」レポート2 |
| 2001年1月 | リック・ジェイスン死亡記事、プロフィールとコンバット以外の出演作品 |
| *コンバットロジー コンバットの様々なエピソードから、登場人物の履歴、性格、家庭環境や部隊の特定などを試みる。 例えば、サンダースはイリノイ州出身で弟が3人と妹が一人いる。所属部隊は、アフリカ戦の経験があり、 オマハに上陸後たびたびイギリス軍と遭遇しているので、第1歩兵師団…などなど。 面白い試みだが、5年に渡って続いたTVシリーズであり、設定もあとから付け足されていったものが多く、 どうしても矛盾点が生まれ、特定には限界があるのはしかたないところ。 そのほかに史実における戦況、軍服・装備品の検証、全放送リストなど。 |
| *コンポート’96 出演者とファンの集い。(配役名)ヘンリー、カービー、ケーリー、リトルジョン、ビリー、カーターの 6人が集合、ファンとともに4日間のメキシコ湾クルーズを通して様々なイベントを楽しんだ。 コンバット・マガジンの記者も招待され、詳細なレポートを載せている。V・モロー亡き後なのが残念。 |
| ★「コンバット!」が表紙を飾ったもの。 | |||
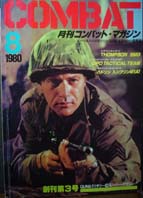 |
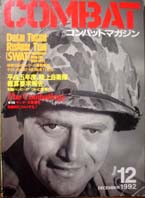 |
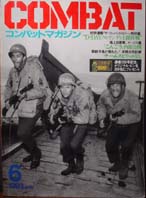 |
 |
| 1980年8月創刊3号 | 1992年12月 | 1993年6月 | 1997年7月 |
| MilitaryToys ミリタリートイズ 2005年8月 Vol.8 “コンバット伝説”というタイトルで記事が組まれている。 番組の説明はコンバットを知らない世代向けの通り一遍 な内容。 後はモデルがサンダース、ヘンリー、カービー、ケーリー、 リトルジョンに扮して現在手に入る装備、エアガンなどを 紹介するという、お気軽なもの。 |
Copyright 2006 S・Sugiyama |
||